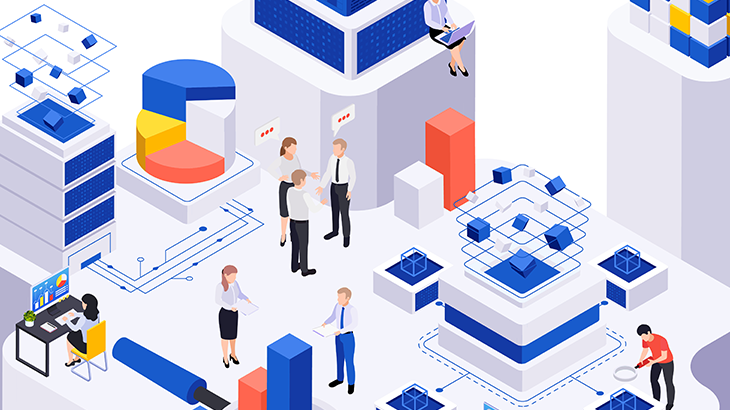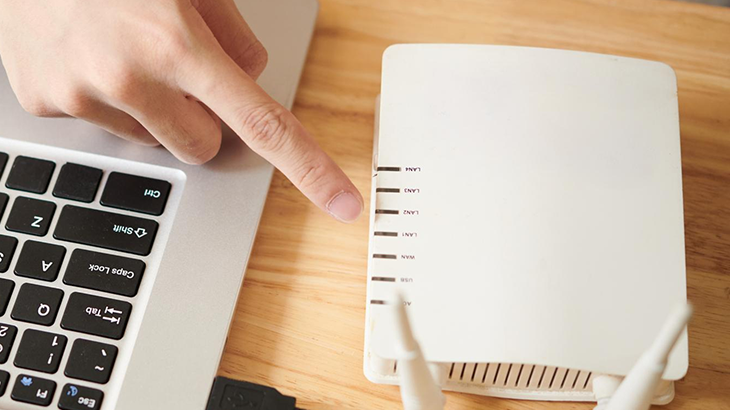※この記事は4月8日時点で執筆しております。情報は更新されている可能性があります。
2025年4月6日未明、高速道路のETCシステムに障害が発生し、計106箇所の料金所が機能不全に陥る
という大規模なトラブルが起こりました。
中日本高速道路は当初、この障害について「5日に実施された深夜割引の仕組み変更に伴うシステム改修が原因」と説明していましたが、
7日の説明会では「別のシステム上の問題が原因である」と修正しました。
この説明が事実であったとしても、
情報の混乱により多くの利用者が不信感を抱いたことは間違いありません。
しかし、今回の件で最も印象的だったのは、
「システム障害発生時の対応について、どこまで想定され準備されていたのか」という点です。
全料金所で同様の対応が取られたかは不明ですが、ある料金所ではETC専用レーンを封鎖し、
一般レーンのみの通行に切り替えたと報じられています。
その結果、各地の料金所付近では大規模な渋滞が発生し、最終的には6日午後に
すべてのレーンを開放、料金未払いでも通行可能とする対応が取られました。
未払い料金については後日精算を呼びかけているとのことですが、
利用者からは「責任を押しつけられた」との印象を持たれても仕方がない対応に見えます。
正直に言って、すべてが後手に回り、現場も混乱していたように感じられました。
システム障害が発生した際、エンジニアが最初に行うのは、
以下のような状況の把握と整理です(少なくとも弊社ではそうしています)
- 現在の状況はどうなっているのか
- 影響の範囲はどこまでか
- 原因はどこにあるのか
- 復旧までにかかる時間はどれくらいか
もちろん、ETCのような大規模かつミッションクリティカルなシステムでは、
調査や判断にも時間を要するでしょう。
それでも、今回のケースでは障害発生から少なくとも9時間以上が
初動調査に費やされたように見受けられます。
さらに6日午後には「システムの切り戻し」が試みられましたが、
これが逆効果となり、それまで問題のなかった12箇所の料金所でも新たな障害が発生。
結果的に被害を拡大させてしまうことになりました。
初動の時点で「調査に時間がかかる」と判断できていれば、
その段階で一時的に高速道路への入場制限を行う等の対策を行う選択肢もあったはずです。
もちろん、その判断は容易ではありませんが、緊急時の対応プランとして事前に想定されていたのか、疑問が残ります。
2025年1月より放送されていたドラマの中で、
消防局の指令システムがダウンするという場面がありました。
作中ではシステム障害が発生すると即座に署にアラートが送られ、
司令部では休憩中の職員も招集され、ホワイトボードや地図帳などを使ってアナログでの対応体制が整えられていました。
フィクションではありますが、このドラマは横浜市消防局が制作に協力しており、実際の対応フローに近いものと考えられます。
人命に関わる業務では、システムが停止しても最低限の業務継続が可能となるよう、
平時からしっかりとした準備が行われているのです。
私たちの仕事もそうですが、業務をシステム化することで効率化や利便性は飛躍的に向上します。
しかし、システムに頼りきっていると、いざという時に対応できず、被害が拡大してしまうリスクがあります。
「もしこのシステムが止まったら、何ができなくなるか?」
「その時、誰が、どのように、どこまで対応できるのか?」
そういった視点で、“システムが止まった時の備え” を定期的に見直しておくことが、
今後ますます重要になると感じさせられる出来事でした。
システム障害への備えは「技術」だけでなく「文化」
私たちのような中小企業であっても、障害発生に備えた準備は不可欠です。
こうした取り組みは、技術面だけでなく「障害が起きたらこう動く」という文化づくりでもあります。
担当者だけに任せるのではなく、部門をまたいだ全体での共有が重要です。
便利な時代だからこそ、「便利が当然」となってしまいがちです。
だからこそ、「非常時の想定と練習」を日常の中に取り入れておくことで、トラブルに強い組織を作ることができます。
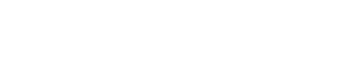

 (3 いいね)
(3 いいね)